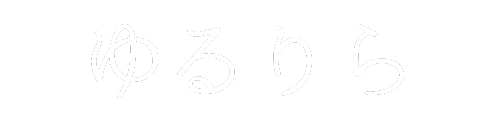こんにちは。「ゆるりら」です。
今日は、「モネ イマーシブ・ジャーニー 僕が見た光」という展覧会を見に行ってきました。
この展覧会は、モネの作品や、彼が“印象派”と呼ばれるに至った経緯などを、体感型デジタルアートという新しい形で紹介しているものです。映像は撮影OK(静止画のみ)だったので、たくさん写真を撮ってきました。
デジタルアートの上映は約30分。会場全体の壁にぐるりと映像が投影され、中央にも垂れ幕のようなスクリーンが垂れ下がっています。床には浮島のようにビーズクッションがいくつも置かれていて、観覧者は自由に腰掛けて鑑賞できるという、なんとも自由で心地よい空間でした。
さらに、スマートフォンでQRコードを読み取ると、無料の音声ガイドを聞くこともでき、私は最近手に入れたAirPodsが大活躍。クリアな音声で解説を聞きながら、まわりの雑音が自然と消える心地よさも体感できました。
とはいえ、そのビーズクッションは人気で、なかなか空きません。ふと見ると、3歳くらいの男の子が一人で座っているクッションがありました。そっと近づいて様子をうかがっていると、その子がママのお膝に駆け寄っていったので、すかさずその席をいただくことに(笑)。お年寄りの方のクッションは空きそうになかったので、ありがたいチャンスでした。
やはり、クッションに座れたかどうかで、この空間の楽しみ方も変わってきますね。朝一番に行って並んで入場したおかげで、まだ空いている時間帯だったのだと思います。
さて、「印象派」とは、なぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。実は、モネの代表作「印象・日の出」を見た批評家が、それを揶揄するかのように「印象派」と呼んだことが始まりだったそうです。でもその批評家の名は後世には残らず、誰よりも先んじて新しい光の表現に挑戦したモネこそが、今も世界中で愛され続けているのです。
この映像体験では、モネの作品が生まれた背景や、彼の人生の軌跡が丁寧に描かれていました。一度の展覧会では到底見ることのできない数々の作品が、時の流れとともに再現され、私は「印象派」とひとくくりにしていたモネが、どんな光を見つめ、どんな想いで筆を動かしていたのかを、あらためて知ることができました。
また、他の画家たちとの友情や確執、流派や信条の違いから起きるいざこざも、どんな世界にもあるものですね。それらは時代を越えればきっと些細なことだったのだろうなと感じ、「もっと仲良くして、たくさん自由に描いてくれたらよかったのに」と声をかけたくなるような気持ちになりました。
会場には、モネの池を模した写真スポットもあり、貸し出し用の日傘も置かれていました。ちょうどそばにいた若いカップルの方にお願いして、記念撮影をしてもらいました(もちろん、おふたりの素敵な写真も撮らせていただきました)。ワンピースを着ていたので、ちょっとモネの世界に溶け込んだような気がして、良い記念になりました。
流派や流儀、中心人物をめぐる争い――それは印象派の時代だけでなく、どの世界にもあるもの。大切にすればするほど、自分の価値観に忠実であろうとすればするほど、ぶつかることもある。でもきっと、それさえもすべて含めて、「表現する」という営みの中で、必要な出来事なのかもしれませんね。